採択率60%超えの秘訣:助成金活用で改修ROIを劇的アップ

ビルの大規模改修は、建物の寿命を延ばし、資産価値を保つために欠かせない経営投資です。しかし、数百万から数千万円に及ぶ費用は、事業者にとって大きな負担となります。そんな中、国や自治体が用意する補助金・助成金制度を活用することで、自己負担を大幅に軽減できることをご存じでしょうか。
特に、建物の省エネ性能向上、防災性強化、用途転換などに対しては、制度的な後押しが年々充実しています。問題は、その制度が「いつ」「どこで」「どんな条件」で使えるのかを把握していないと、せっかくのチャンスを逃してしまうという点です。
今回のお役立ち情報では「ビルの大規模改修に活用できる補助金・助成金の制度と、採択率を上げる申請のコツ」について解説します。
▼合わせて読みたい▼
高すぎる見積もりを斬る!データで示す適正価格と交渉術
助成金・補助金を使うと何が変わるのか?

補助金や助成金を上手く活用すれば、改修にかかる初期コストを圧縮できるだけでなく、長期的な収益性やテナント満足度の向上にもつながります。たとえば、自己負担を500万円減らすことができれば、その分の資金を別の投資や維持管理に回すことが可能です。
一方で、制度に頼りきった計画を立ててしまうと、申請が通らなかった場合に工事がストップしてしまうといったリスクもあります。つまり、補助金活用は「魔法のツール」ではなく、経営判断を左右する戦略的要素として捉えることが必要です。
大規模改修の費用構造と助成金による負担軽減効果
ビルの大規模改修にかかる費用は、主に以下のような構造になっています。仮設足場の設置、外壁の塗装・補修、屋上の防水工事、シーリング打ち替え、そして場合によっては空調・給排水などの設備更新。このうち仮設や塗装だけでも全体の3〜4割を占めることが多く、工事規模によっては1,000万円を超えることも珍しくありません。
助成金や補助金の中には、このうち省エネ対策部分や耐震・防災に関わる項目に対して、最大で3分の1〜2分の1の補助が出る制度もあります。仮に1,500万円の改修工事に対して500万円の助成が得られたとすれば、ROI(投資対効果)は大きく改善されることになります。
とくにエネルギーコスト削減を見込める設備投資を含めた改修では、補助金を導入することで「先出しコスト」が実質的に数年で回収できる試算になるケースもあります。
実際にROIが上がった活用事例
ある商業ビルでは、空調更新と断熱強化を組み合わせた省エネ改修に、国の補助金を活用して工事を実施しました。総工費約1,200万円のうち、450万円が補助金として交付され、実質の自己負担は750万円になるわけです。これにより、月々の電気代が平均15%以上削減され、5年以内に補助金額以上の光熱費節約効果が見込める結果となりました。
また、補助金活用によって浮いた予算を活かし、エントランスの意匠改修やバリアフリー化も実施したことで、テナント満足度も向上。翌年度の賃料改定交渉において有利に働いたという報告もあります。
このように、単に「費用を減らす」という目的にとどまらず、収益構造を改善する一手として助成金は非常に有効です。
「助成金ありき」で計画すると失敗する理由
多くのオーナーや管理会社が陥りやすいのが、「補助金が出るからやろう」という逆算的な発想です。確かに助成金の存在は魅力ですが、申請には書類準備・審査期間・実績報告など、煩雑な手続きがつきものです。さらに、審査に落ちれば一銭も交付されないという前提を忘れてはいけません。
とくに2024年度以降は、申請倍率の上昇や電子申請限定制度の拡大によって、採択率が低下傾向にある自治体も出始めています。あくまでも「自前でやる計画を立てて、助成金は採れたらラッキー」というスタンスで設計を進めるほうが、結果的に無理のない改修が実現します。
資金計画に助成金を組み込むなら、必ず不採択時の代替案や予備資金も視野に入れておくべきです。
▼合わせて読みたい▼
資産価値10年先取り!ビル大規模改修で競争力を守る経営戦略
2024年度に使えた大阪の主な補助金制度

2024年度、大阪市ではビルの大規模改修に活用できる補助金制度が複数存在しました。特に省エネ性能の向上や耐震性の強化、空き家の有効活用を目的とした制度が充実しており、適切に活用することで改修費用の軽減が可能でした。
実際に2024年度に利用できた主な制度と、その概要を紹介します。
住宅省エネ2024キャンペーン
「住宅省エネ2024キャンペーン」は、国土交通省、経済産業省、環境省が連携して実施する、住宅の省エネルギー化を支援する補助事業です。このキャンペーンは、以下の4つの補助事業で構成されています。
- 子育てエコホーム支援事業
- 先進的窓リノベ2024事業
- 給湯省エネ2024事業
- 賃貸集合給湯省エネ2024事業
これらの事業を通じて、断熱性能の向上や高効率給湯器の導入など、省エネ改修を行う際の費用の一部が補助されます。補助金額は最大280万円とされており、特に子育て世帯や賃貸住宅のオーナーにとっては、大規模改修の費用負担を軽減する大きな支援となりました。
ただし、予算には限りがあり、申請期間中であっても予算が終了次第、受付が締め切られるため、早めの申請が推奨されました。
民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度
大阪市では、地震に強い安全なまちづくりを目指し、民間住宅の耐震化を促進するための補助制度を設けています。この制度は、昭和56年5月31日以前に建築された住宅を対象に、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事、耐震除却工事に要する費用の一部を補助するものです。
具体的な補助内容は以下の通りです。
- 耐震診断:1戸あたり最大5万円、1棟あたり最大20万円
- 耐震改修設計:1戸あたり最大10万円、1棟あたり最大18万円
- 耐震改修工事:1戸あたり最大100万円
- 耐震除却工事:1戸あたり最大50万円、1棟あたり最大100万円
これらの補助を活用することで、老朽化したビルの耐震性能を向上させ、入居者の安全性を確保することが可能となります。申請には、耐震診断の結果や設計図面などの提出が必要であり、事前の準備が重要です。
空家利活用改修補助制度
大阪市では、空き家の有効活用を促進するため、「空家利活用改修補助制度」を実施しています。この制度は、空き家を住宅や地域まちづくりに資する用途に改修する場合、その費用の一部を補助するものです。
補助対象となる工事には、インスペクション(既存住宅状況調査)、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事、性能向上に資する改修工事、地域まちづくりに資する改修工事などが含まれます。
補助金額は、住宅再生型で最大75万円、地域まちづくり活用型で最大300万円とされており、改修内容や用途によって異なります。この制度を活用することで、空き家を有効に活用し、地域の活性化や住宅ストックの有効活用を図ることができます。申請には、耐震性の確保や改修計画の提出が必要であり、詳細は大阪市の公式サイトで確認することが推奨されます。
これらの補助制度を活用することで、ビルの大規模改修にかかる費用を軽減し、建物の性能向上や資産価値の維持・向上を図ることが可能です。ただし、各制度には申請条件や期限が設けられているため、事前に詳細を確認し、計画的に進めることが重要です。
2025年度にスタートした注目制度と申請のコツ
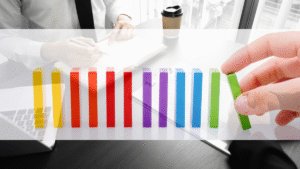
2025年度、大阪市および大阪府では、ビルの大規模改修に活用できる新たな補助金制度が開始されました。これらの制度は、省エネルギー性能の向上や耐震性の強化を目的としており、適切に活用することで改修費用の軽減が可能です。
省エネ改修・災害対策型の新制度
2025年度、大阪市では「住宅の省エネ改修費補助制度」が開始され、省エネルギー性能の向上を目的とした改修工事に対して補助金が支給されるようになりました。
この制度では、開口部(窓やドア)の断熱改修や、屋根・外壁・床の断熱工事、高効率給湯器やLED照明などの設備導入が補助対象となります。補助率は、省エネ基準レベルで補助対象事業費の2/5(上限30万円)、ZEHレベルで4/5(上限70万円)とされており、改修の規模や内容に応じて適用されます。
これにより、ビルのエネルギー効率を高め、ランニングコストの削減が期待できます。
また、大阪府では「中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援補助金」が実施されており、府内の中小事業者が省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備の導入を行う際に、補助金が支給されます。
この制度では、事業所全体の年間エネルギー使用量を1%以上削減する事業や、二酸化炭素排出量を年間1トン以上削減する事業が対象となります。補助金の申請には、対策計画書の提出や脱炭素経営宣言の登録が必要であり、計画的な取り組みが求められます。
採択率60%超えを実現した申請フローの共通点
補助金の採択率を高めるためには、申請フローの各ステップを丁寧に進めることが重要です。
まず、補助金の対象となる工事内容や条件を正確に把握し、計画段階から補助金の要件を満たすように設計を行うことが求められます。次に、必要な書類を漏れなく準備し、提出期限を厳守することが基本です。
とくに、工事の見積書や設計図面、エネルギー削減効果の試算など、具体的な数値や根拠を示す資料が採択の可否を左右します。
また、申請前に自治体の担当部署と事前相談を行い、申請内容の確認やアドバイスを受けることも有効です。
これにより、申請書類の不備や誤解を防ぎ、スムーズな審査につながります。さらに、補助金の申請代行を行う専門業者に依頼することで、申請手続きの効率化や採択率の向上が期待できます。これらのポイントを押さえることで、採択率60%超えを実現した事例も報告されています。
申請のタイミングと注意点(2025年度版)
補助金の申請においては、タイミングと注意点を把握することが成功の鍵となります。多くの補助金制度では、申請受付期間が設けられており、予算が上限に達した時点で受付が終了する場合があります。そのため、補助金の公募情報を早期に収集し、申請準備を前倒しで進めることが重要です。
また、申請には多くの書類や手続きが伴い、不備があると審査に時間がかかる、あるいは不採択となる可能性もあります。特に、2025年4月からは建築基準法の改正により、木造戸建ての大規模なリフォームが建築確認手続きの対象となるため、建築確認済証の写しや検査済証の添付が必要となる場合があります。
これらの法改正にも注意を払い、必要な手続きを漏れなく行うことが求められます。
さらに、補助金の申請から交付決定までには数週間から数ヶ月の審査期間がかかるため、工事のスケジュールにも余裕を持たせることが望ましいです。これらの点を踏まえ、計画的かつ慎重に申請を進めることが、補助金の活用を成功させるためのポイントとなります。
以上が、2025年度にスタートした注目の補助金制度と申請のコツです。これらの情報を参考に、ビルの大規模改修における補助金の活用を検討してみてください。
コストを投資に変える、助成金活用の戦略思考
ビルの大規模改修は、避けて通れないコストであると同時に、資産価値や収益性を左右する重要な経営判断です。そこで補助金・助成金という選択肢を取り入れることで、単なる支出を「投資」へと転換することが可能になります。
ただし、制度にはタイミングや条件、提出書類の整備など乗り越えるべき壁もあります。申請ありきではなく、自社の改修計画に合う制度を精査し、採択されるだけの根拠を持って挑むことが成功のカギです。
制度の仕組みを知り、採択率を引き上げる「設計と準備」こそが、ROIを最大化させる最短ルート。助成金を「使う側の戦略」が問われる時代が、すでに始まっています。
採択率60%超えの秘訣:助成金活用で改修ROIを劇的アップ|株式会社エースのご提案

ビルの大規模改修にかかる費用は数百万円から数千万円に及びますが、国や自治体の補助金・助成金制度を賢く活用すれば、初期コストを大幅に圧縮でき、長期的な収益性向上やテナント満足度アップに繋がります。
特に省エネ性能向上や耐震補強、用途変更に対する制度は年々充実しており、最大で工事費用の3分の1から半額程度の補助を受けられるケースもあります。しかし、申請のタイミングや条件を見極め、必要書類の準備と行政との事前相談を丁寧に行わなければ、せっかくのチャンスを逃すリスクも高まります。
株式会社エースでは、大阪市・豊中市エリアの最新補助金制度情報を踏まえ、採択率60%超えを実現した申請フローを多数手掛けています。具体的には、補助対象工事の正確な把握、工事計画段階からの制度適合設計、根拠ある見積・エネルギー削減効果の試算提示、そして行政との綿密な連携を推進。これにより、多くの案件で高い採択実績を誇ります。
また、助成金を前提とした無理な計画ではなく、「自社資金で実現可能な計画を立てたうえで助成金を活用する」という戦略的なスタンスを推奨し、不採択時のリスクヘッジも十分に考慮しています。
助成金の活用は単なる経費削減ではなく、資産価値維持・向上のための有効な経営戦略です。申請書類の準備や申請代行、採択に向けた各種サポートも株式会社エースにお任せください。お問い合わせフォーム、メール、電話、ショールーム来店にて詳細なご相談を承っております。
補助金活用で賢くコストを抑え、改修投資のROIを最大化するなら、ぜひ株式会社エースにご相談ください。
▼合わせて読みたい▼
株式会社エース|会社情報
無料相談・お見積りはこちら
物件の状況・ご計画に即した最適解をご提案します。下記に物件概要とご要望をご記入ください。担当者が内容を精査のうえ、概算費用・工程案・進行スケジュールをご連絡します。
※ 営業のご連絡はご遠慮ください(誤送信時は対応費 5,000円のご案内あり)。